「向いてないかも」キャリアを諦めかけた歯科医師がOralXに出会うまで

日々忙しく働く中、「この環境で学び続けるのか」「体系的に知識が身についたのか」と悩みながら働く歯科医師の方も多いはず。
一般社団法人OralX(以下:OralX)で「東京新宿矯正歯科」院長として活躍する歯科医師の佐藤さんも、同じ悩みを抱え、歯科医師以外のキャリアを考えることもありました。
そんな悩みを持っていた佐藤さんはOralXと出会い、今では「より適切な提案を届けたい」というまっすぐな思いで日々ユーザーと向き合っています。
どんなことに悩み、OralX入社後どう変わったのか。
この記事では、佐藤さんにOralXで働くことのリアルな姿についてお聞きしました。
※一般社団法人OralX:若者から支持されるマウスピースブランド「Oh my teeth」を専門に取り扱う矯正歯科医院。東京・大阪・名古屋・福岡で複数ストア(医院)を展開中。「未来の歯科体験を生み出す」をミッションに掲げ、直近ストア来店者数(来患数)は5万人を突破しました。従来のマウスピース矯正の難点である「値段が高い」「通院が面倒」「つづけられない」を解決する「Oh my teeth」ブランドを専門で提供しています。
“見て学ぶ”だけに限界を感じた。
──OralXでの仕事内容を教えてください。
佐藤さん:現在は新宿ストアの院長として、来店したユーザーのスキャンデータを確認後、歯科衛生士メンバーと協力しながらプラン診断をしています。診断は症例レベルに合わせて大きく分けて5パターン*があり、その中から最適なプランを見極めることが醍醐味です。
2025年6月時点で、ライト、ベーシック、プロのOh my teethブランドの3段階、インビザライン、SmileGo(他歯科医院への紹介)の5パターンを展開しています。
OralXは業務の切り分けが面白くて、歯科医師は診断、IPR、アタッチメントの処置全般に関わること。歯科衛生士さんは、3Dスキャン対応、プランの提案などの来店ユーザーの対応全般を担当しています。歯科医師が偉いなどはないので、あくまでフラットなチームの一員として働いています。
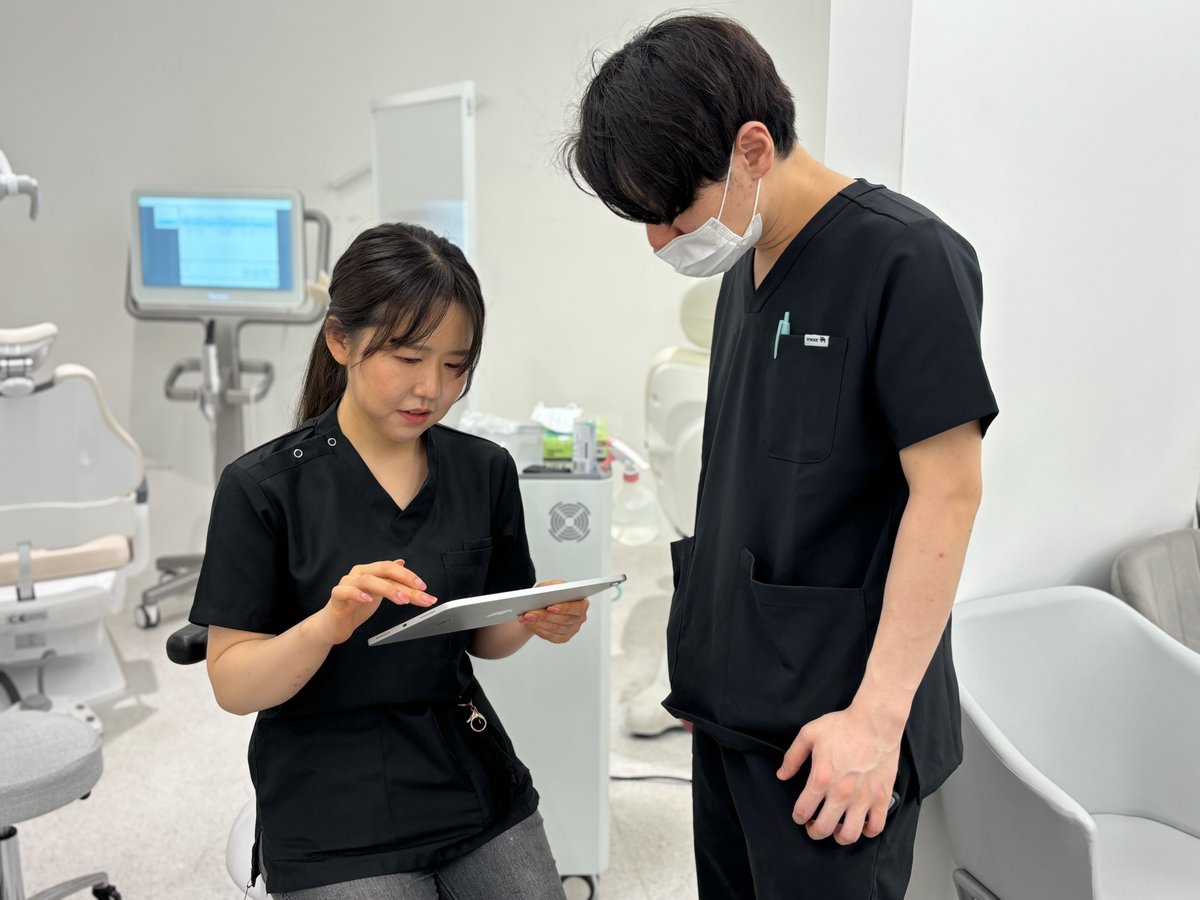
── 以前は一般歯科でお勤めされていたと聞きました。
大学卒業後は複数人の勤務医がいるようなそれなりの規模の一般歯科に勤めたんです。
あるあるだと思いますが、一般歯科の現場は忙しいので基本的に研修はありません。大学で学んできてるからとりあえずやってみようと言うのが主流、“見て学ぶ”的なイメージですね。
もちろん困ったことがあれば優しい先輩たちだったので聞くこともできましたが、「いちいち聞くのもな…」と遠慮してしまうところが正直ありました。
また、一般歯科はOralXの様に分野に特化していないので、予防歯科〜根っこの治療、外科手術まで幅広いことに対応しなければなりません。シングルタスクよりは、マルチタスク。
マルチタスクな現場を経験した分、幅広い知識が身につくのですが、体系的にノウハウが整理がされていることは決して多くありません。時間もないので、指導の仕方も症例発生ベースでこの場合はA、あの場合はBと言う感じが基本です。
知識が積み重なると言うよりは、後出しジャンケンの感覚で知識が横に増えることが多かったので少し不安を感じていました。
── 現場経験以外に知識を身につける機会などはあるのでしょうか。
基本的にはセミナーなどの外部イベントへの参加がメインでした。一般歯科は学ばなければいけないジャンルが多岐に渡ります。現場で起きたベースで学んでいっても、結局イタチごっこ感は拭えませんでした。
参加費用についても、OralXの場合は補助がありますが、当時の歯科医院は自己負担の部分もあり、時間的にも金銭的にも焦っていたのが本音です。
現場は本当に忙しいので、歯科業界全体がこういう教育風潮になることは理解していました。だからこそ、歯科業界の当たり前に馴染みきれない私は、向いてないんだ。そう思う様になりました。
OralXとの出会い
── そんな忙しい日々の中、どのようなきっかけでOralXを知ったのですか。
歯科医師は向いてないなと思っていたときに、好きなブランドの商品開発の求人を覗いていました。その時に偶然、OralXの求人がヒットしたんです。
今までマルチタスク的な学び方をしなければいけないという不安から歯科医師を諦めかけていましたが、一つの分野に特化すれば「不安なく働けるかもしれない」と微かな希望を感じて応募しました。
── 実際に入社してみてギャップはありますか。
良い意味で結構ありますね。
今までと研修体制、業務内容、雰囲気などあらゆるものが違っていました。今は本当にストレスフリーです。より良い体験を届けるという、然るべきことに時間も頭も使えている感じがあります。
研修体制で言えば、ベースの診断やIRPなどはかなり丁寧に教えてもらいました。だいぶしっかりめだと思いますよ。
座学で原理原則を学んだ後、入社1ヶ月ほどは先輩についてOJT指導を受けます。人に合わせてくれますが、まずは見て、次に難易度の低いものから取り組み、適宜アドバイスをもらえるので、かなり助かりました。
OralXは全ての診断にダブルチェック体制がひかれているので、独り立ちした後も学べることは多いです。ダブルチェックと現場の診断が食い違ったときには意見を交換することができます。そしてそれはSlackというオープンなコミュニケーションツール上で行われるので、他の人の診断ケースからも学ぶことができます。IPRなども研磨量など困ったことがあればいつでもアドバイスがもらえます。
何よりすごいのは聞きづらさが少しもないんです。理事長の本多さんをはじめ、全員がまず人として対等に扱ってくれ、質問にきちんと答えてくれます。特別なことではないかもしれないのですが、そんな当たり前の積み重ねがこの空気感を作っているのではないかなと。
私が業務バランスをうまくコントロールできなくなった時にも、私よりも何倍も忙しいドクターが気にかけてくれたりと、温かい人が本当に多いです。

──最近楽しいと感じたことはありますか。
メンバーと話すことが楽しいですね。他の歯科医院も歯科衛生士と歯科医師は対等だと掲げることは多いと思うんですが、現場に入ると実態とのギャップを感じてしまう歯科医院も多いと思います。ただ、OralXは本当に対等に扱っているんだなと入社の時から感じています。
OralXには自分にはない強みを持った人たちが集まってる感じがするんですよね。歯科衛生士さんは私よりユーザーに合わせて話すのが得意ですし、ユーザー獲得のチームはマーケティングが、技術開発のエンジニアやラボは専門性が、とそれぞれの特色がはっきりしています。
私が助けてもらうことも多くあります。
歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、マーケティングなど、これら全てのチームが揃って初めてユーザーに価値を届けられるということを最近やっとわかってきました。
これは歯科医師がてっぺんの階層構造ではなく、OralXの本当にフラットな組織構造が作り出しているのではないかと思っています。
この部分を面白いと思うのは、今まで歯科業界っていう特定の世界にいた分の反動かもしれないですね。
──これからどんなことを頑張りたいと思っていますか。
いくつかあるのですが、一つは、歯科医師としての技術クオリティ。IPRなど。もう一つは歯科衛生士メンバーがより良い提案をユーザーにできるように、矯正診断スキル、専門用語をわかりやすく翻訳することなどを意識したいと思っています。
関わりたいと思える様な人たちが多いからこそ、周りに還元をしたい、そう強く思っています。
編集後記
インタビュー当初は、笑顔で働く佐藤さんのイメージでしたが、実は悩みながらここまで至ったという部分がとても印象的でした。
フラット、アットホーム、オープンな組織。この言葉はよく使われますが、それが飾りになっては意味がない。対等なチームの中で、自分たちが価値を提供するべき相手のことをまっすぐ考えられる、そんな環境がOralXにはあります。
もし、あなたが「歯科医師に向いていないかもしれない」、そう思うのであれば、一度OralXの新しさを、ご自身の目で確かめてみてください。

採用ホームページはこちら
Oh my teethについてはこちら